校長散歩

2025.07.14
- #授業
- #チャレンジ
793 特別授業「武蔵百年の森プロジェクト」キックオフ講演会
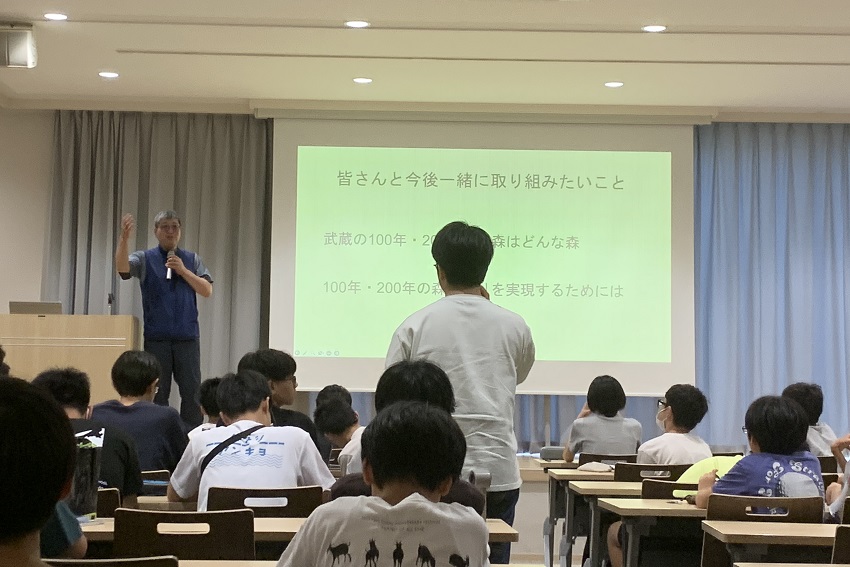
7月7日の5、6限、特別授業の一環として、視聴覚室を会場に、「武蔵百年の森プロジェクト」キックオフ講演会を開催しました。中1から高2まで60名あまりの生徒が参加しました。
「武蔵百年の森プロジェクト」とは、埼玉県毛呂山町にある武蔵学園の「学校山林」を、次の百年に向けて再生していこうという取り組みです。この「学校山林」は、日本紀元2600年(1940年)の記念事業として、当時の父兄会(現在の保護者会)からの寄付金により土地を購入し、植樹等を行ったことをはじめとしています。その後、現地近くの方に管理人をお願いして維持管理に努め、1960年以来、毎年春に、入学したばかりの中学1年生が「山林遠足」としてこの地を訪れて、親睦を深めるとともに武蔵の精神を学んでいく場ともなっています。一方で、長らく管理を託していた管理者が退官され、その後、「学校山林」をどう継承させていくかが課題となっていました。
そんな折り、新たな管理指導者として『NPO法人しんりん』の大場隆博理事長をお迎えすることができました。大場さんは、これまでも校長散歩504や副校長散歩でご紹介したように、武蔵において地域活性化のお話をしていただいたり、実際にフィールドワークでご協力いただいていたりした縁もあり、このプロジェクトに御協力いただけることになりました。
大場さんは宮城県鳴子温泉にあるリゾート開発で失敗した森を「エコラの森」として蘇らせる取り組みをされてきた方です。また、単に木を切る林業ではなく、産出される木材を余すことなく利活用するなど、木材加工業者やエネルギー業者、さらには教育関係者とも協働し、「地域循環共生圏」の確立に向けて、豊かな知見とつながりを持たれています。
この日は、わざわざ宮城からお越しいただき、「いま森を守ることの意義はどこにあるのか?」という演題で語っていただきました。まず生徒たちに、概論として、そもそも日本は森林面積が大きいにもかかわらず、建築材の多くを輸入に頼っていること、さらにそうした木材が違法伐採によってもたらされているという現状の話から始まり、そうした現状を打開すべく、今後、取り組むべき方向性として、持続可能な森づくりや循環と共生を可能とする地域づくりへの道筋まで、分かりやすくお話をしていただきました。さらに、武蔵の学校山林も今は手入れがされていないかもしれないけれど、大いに可能性がある。計画的に間伐作業を行いつつ、広葉樹と針葉樹の混じった「針広混交林」に向けて森づくりを行う中で、その間伐材を、例えば学校の施設設備にも生かすなど、余すことなく森林を活用する可能性があることについて語っていただきました。
環境教育さらにはSDGs教育の重要性が言われています。まさにこのプロジェクトは、それにかなったものだと思います。これからの百年という未来を見据えて、武蔵の森を育てるため、今後、生徒有志のコアメンバーも募りながら、武蔵ならではのプロジェクトを進めていきたいと考えています。本日は、そのキックオフが順調にできたと思います。
この日、遠くからわざわざお越しいただいた大場さんに感謝申し上げるとともに、今後ともよろしくご指導いただきたいと考えています。
